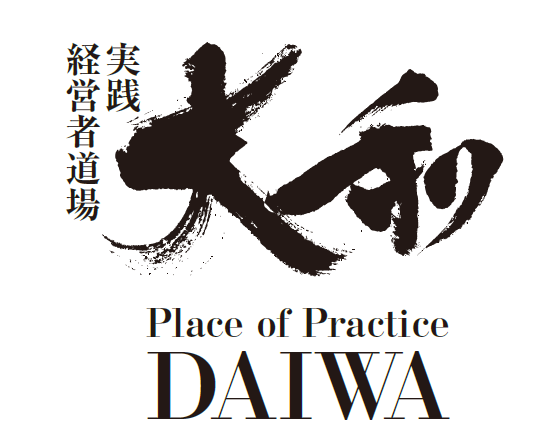
盛和塾〈大阪〉から、実践経営者道場《大和》へ
1983年、京セラ・KDDI創業者である稲盛和夫氏のもとに京都の若手経営者たちが「経営の要諦を教えてほしい」と懇願して始まったのが盛友塾。間も無く、この学びを自分たちのものだけにしていてはもったいないと塾生たちが塾長に進言して全国展開が決定。「盛和塾」という名称は当時の大阪塾代表世話人らが提案し、採用されました。
以後、各地で自主的に盛和塾を立ち上げる経営者らによって広がり、国内56塾、海外48塾、塾生総数は15,000人を超えるまでになりました。2019年、87歳になられた稲盛氏は解散を宣言。大阪では再び、この学びを自分たちのものだけにしてはいけないと、率先して趣意書を届け、歴代代表の尽力を経て実践経営者道場《大和》が立ち上がりました。
《大和》の由来
読み方は「だいわ」。稲盛和夫氏が得度された際の法名に由来します。企業家とは単に利益集団をつく
るのではなく、人という命の成就とすべての命や存在の和合を生き、育てる使命を意味するとされて
います。大阪塾はこれを機に、地域を超え世代を超えた「だいわ」を目指してまいります。
| 1989年 | 盛友塾(1983年京都で発足)の在阪有志の提案により大阪支部と名称「盛和塾」が誕生。 盛和塾〈大阪〉が発足する |
| 1991年 | 100塾5,000人構想(全国組織化趣意書発行) |
| 2008年 | 大阪塾 五百羅漢(塾生数500名達成) |
| 2009年 | 大阪塾 七福神(塾生数700名達成) |
| 2010年 | 稲盛和夫(元盛和塾塾長)のJAL会長就任を受け、大阪塾発起により「JAL応援団-JALを 支援する55万人有志の会」結成 大阪塾 千哉瓢箪(塾生数1,000名達成) |
| 2019年 | 盛和塾 解散に伴い盛和塾〈大阪〉12月をもって解散 |
| 2020年 | 実践経営者道場〈大和〉発足/塾生数550人 |
実践経営者道場≪大和≫の活動は、塾生会員自身により運営されています。
大阪駅前第三ビル28階の第1道場、第2道場を拠点とし、必要に応じて外部の施設を使用。
事務局は、盛和塾〈大阪〉事務局の体制を引き継いでいます。
また、関西圏の旧・盛和塾10塾とも連携しています。
[2024年度 世話人一覧]
代表世話人
栗田 佳幸・今井 真路・黒田 基仁
世話人(50音順)
礒川祐二・井上善博・上田昌弘・内畑谷 剛・小川 健・笠嶋 勲・門田 恵理子・小倉弘好・小西繁雄・久保篤志・齊藤美雪・重延賢治・末松仁彦・谷口善紀・原田智樹・橋本明元・森岡昇馬・南島忠男

|
共に高め合う
|
実践経営委員会(月1回) 全塾生は5経営委員会のいずれかに所属。稲盛氏の講話映像に学んだり、塾生自身の経営体験発表を通じて利他の心で対話し、互いにより良い経営に向けて深めあいます。合宿研修やコンパなど工夫を凝らしたプログラムで、互いの経営を伸ばす真摯な学びの場をつくります。塾生は、所属以外の勉強会への参加も可能です |
|
志の実践へ
|
選抜合同自主例会(月1回) 経営体験発表者の中から選ばれた経営者による経営体験発表や盛和塾OB、地域塾生らの経営体験発表をもとに、自らの気づきをひらく《大和》塾生全員参加の勉強会。他塾生も参加し、より深い対話を1日かけて行います。選抜合同自主例会を経て、全国の旧盛和塾関連塾が集う世界大会に進出する道筋にもなっています。 |
|
志を高める
|
合宿研修会(月1回) 大阪塾 五百羅漢(塾生数500名達成)自らの良心を磨き、心を高めて経営を伸ばすために熱く学び、語り合う2日間。合宿だからこそ得られる心の繋がりもあり、魂が震えるような自身の気づき、実践へのエネルギーを共創する機縁に満ちています。次世代につなぐ幸福な経営、幸福な社会づくりに向けて良心を磨きあう共働態になる場でもあります。 |
|
実践を広げる
|
あきんど祭り(年1回) 大阪・高津宮を舞台に塾生企業による出店と催しで地域貢献を実践する機会。商いの原点にかえり、生活者や地域社会とつながりながら、「屋台でも成功する」経営哲学を磨きあいます。年に一度の祭典に終わらず、地域への貢献を考え続け、実践を広げ続けて、永続的な経営のあり方を能動的参画によって学びます。 |
|
数字に強くなる
|
会計学講座 一般公開講座(フィロソフィ勉強会) |
実践経営者道場《大和》はコロナ禍にスタートを切りましたが、大阪駅前第3ビルの道場において、オンライン配信設備を整え、ハイブリッドでの開催も可能になっています。